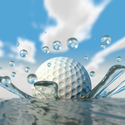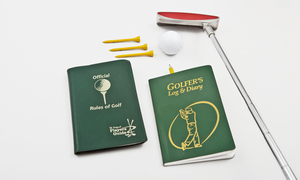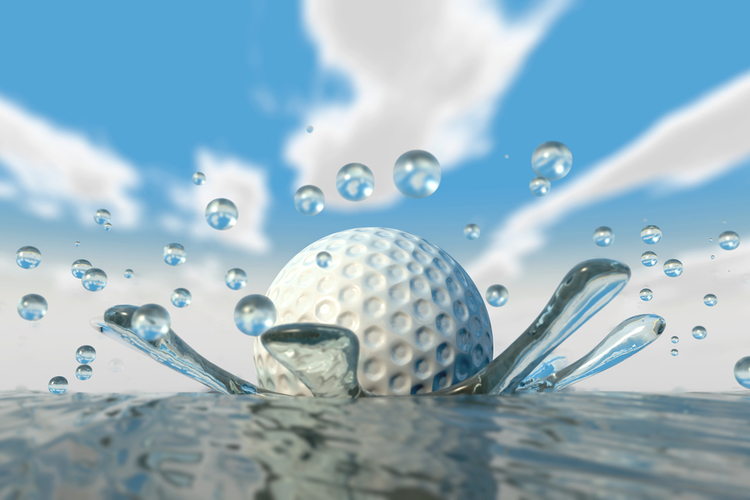
ゴルフルールのややこしい点の代表例が池などの「ペナルティエリア」に関する項目です。赤杭と黄杭で救済の方法が違ったり、救済の基点の決め方が難しかったりで、救済措置を間違えやすいエリアとなっています。救済の方法を間違えてしまうと「誤所からのプレー」となり、池ポチャの1打罰に加えて、さらに2打のペナルティが課されます。
本記事では「ややこしい」と感じる方が多いペナルティエリアでのゴルフルールをまとめています。ぜひお役立てください。
【2019年版】ゴルフルール集〜ペナルティエリア編〜

ペナルティエリアとは?
2019年から施行された新規則では、コース内のプレーエリアは「ティーイングエリア」「ジェネラルエリア」「パッティンググリーン」「バンカー」「ペナルティエリア」に分類されています。
本記事のテーマとなっているペナルティエリアは、旧ルールではウォーターハザードやラテラルウォーターハザードと呼ばれていた区域が該当します。新規則では水域以外にも、崖や林などゴルフ場が1打罰での救済措置を認めたいエリアも指定できるようになっています。
球の確認について
2018年まで適用されていた旧ルールでは、球の確認のためにペナルティエリア内の球を拾い上げることは反則行為とされていました。
2019年から施行されている新規則では、ペナルティエリア内であっても確認のために無罰で球を拾い上げることができるようになりました。
他のエリア同様に、球についた汚れは確認に必要な量であれば落とすことも認められています。必要以上に汚れを落とすと、2打のペナルティが課されますのでご注意ください。
ペナルティエリア内からのショットについて
打った球がペナルティエリア内に止まった際は、必ず罰打と救済を受ける必要はなく、そのままプレーを続けることもできます。ペナルティエリア内の球を打つ際、2018年まで適用されていた旧ルールでは、クラブをソールする(地面につける)ことが禁止されていました。2019年から施行された新規則では、ペナルティエリア内でもクラブをソールすることが認められ、ジェネラルエリアと同じようにプレーできるようになりました。
黄杭と赤杭の違いについて

ペナルティエリアは黄杭または赤杭によって領域が指定されており、その種類によって受けられる救済が異なります。2018年まで適用されていた旧ルールでは、黄杭に囲まれたエリアは「ウォーターハザード」、赤杭に囲まれたエリアは「ラテラルウォーターハザード」と呼ばれていました。2019年から施行された新ルールでは、前者は「イエローペナルティエリア」、後者は「レッドペナルティエリア」という名称に変わっています。
イエローペナルティエリア(旧ウォーターハザード)の救済
打球がイエローペナルティエリア内に入った場合、スコアに1打罰を加算することで以下の3つのうち、いずれかの救済を受けることができます。
①球が最後にエリアとの境界線を横切った地点から、1クラブレングス以内かつホールに近づかない範囲内にドロップ
②球が最後にエリアとの境界線を横切った点とホールの後方線上に基点を作り、その基点から1クラブレングス以内の範囲にドロップ
③元の位置に戻って打ち直し
※2018年まで適用されていた旧ルールでは、救済エリアを計測するクラブは指定されていませんでしたが、2019年から施行されている新規則では、携帯しているクラブの中で最も長いもの(パターを除く)に変更されました。多くの方はドライバーがエリア計測のクラブとなります。
レッドペナルティエリア(旧ラテラルウォーターハザード)の救済
レッドペナルティエリアはコースサイドに沿って池やクリークが伸びているなど、後方線上の救済措置が地形的に難しい箇所が指定されていることが多く、イエローペナルティエリアの3種類の救済方法に、以下の救済措置が選択肢として加わります。
④球がエリアとの境界線を最後に横切った地点から2クラブレングス以内かつホールに近づかない範囲内にドロップ
※2018年まで使われていた旧ルールでは最後に球がエリアとの境界線を横切った点とホールを結ぶ線を半径とする円上であれば、池やクリークの対岸にも救済の基点を作ることができましたが、2019年から施行された新規則ではそれができなくなっています。
ドロップの手順
①受ける救済の種類を選択したら、救済の基点を作り、マークする。
②基点から2クラブレングスまたは1クラブレングスかつホールに近づかない範囲をドロップエリアとして指定する。
③指定したエリア内に膝の高さからドロップし、エリア内に球が止まった場合はプレーを再開。エリア内に球が止まらなかった場合は再ドロップし、それでも球がエリア内に止まらない場合は、2度目のドロップで球が最初に接地した点にリプレースしてからプレーを再開する。
※2018年まで適用されていた旧ルールでは、球をドロップするときは「肩の高さ」からと決められていましたが、2019年から施行された新規則では「膝の高さ」からに変更されています。
障害物について

ゴルフ規則で「障害物」とは、コース内でプレーに影響を及ぼす人工物と規定されており、「動かせる障害物」と「動かせない障害物」に分類されます。
前者はタバコの吸い殻などのゴミやペナルティエリアを示す杭、カート道の案内板などが該当し、後者は茶店などの建造物、排水溝、スプリンクラーなどが該当します。
「動かせる障害物」の取り扱いについて
動かせる障害物がプレーの邪魔になる場所にある場合、不当にプレーが遅らせることがないことを条件に、別の場所に移動させることができます。
ペナルティエリアの範囲を示す、赤や黄色の杭も「動かせる障害物」に該当し、すいイングの邪魔になる場所にある場合は、抜いてからショットすることも可能です。
(同じ杭でもOBの範囲を示す白杭は「動かせる障害物」に該当しません。プレーの邪魔になるからといって動かしてしまうと、2打のペナルティが課されますのでご注意ください。)
「動かせない障害物」の救済について
動かせない障害物がショットの妨げになる場合は、球があった位置から最も近く、ホールに近づかずスタンスが取れる位置(ニアレストポイント)から1クラブレングス 以内の場所にドロップすることができます。
ただし、ペナルティエリアとバンカーの範囲内では、「動かせない障害物」の救済は適用することができません。お間違いのないよう、ご注意ください。
ルースインペディメントについて
ルースインペディメントとはコース内に散在する自然物で、木の葉や小石などプレー中は無意識に取り除いてしまうようなものを指します。「動かせる障害物」と混同しがちなのですが、「動かせる障害物」が基本的に人工物であるのに対し、「ルースインペディメント」は自然物という違いがあります 。
2018年まで適用されていた旧ルールでは、バンカー内、ペナルティエリア内のルースインペディメントを取り除くことは禁止されており、違反した梅には2打のペナルティが課されていました。
2019年から施行された新規則ではこの罰打が廃止され、すべてのエリアでルースインペディメントを動かすことができるようになりました。ただし、ルースインペディメントを動かしたことが原因で球が動いてしまった場合は、1打罰で元の位置にリプレースしなければなりません。取り除く際は球を動かさないよう、お気をつけください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。ちょっとややこしいペナルティエリアのルールはマスターできましたか?仲間内のプライベートなラウンドでは「そのあたりからでいいよ〜」となることもありますが、正しい救済の方法を知っておいて損はありません。
ルースインペディメントを取り除けるようになったなど、2019年からの新規則では知っていると有利にプレーを進められる内容も多くなっています。上手に活用して、ゴルフライフをさらに充実させていただければ幸いです。
ラウンド時に持ち歩ける「JGA 2019年ゴルフ規則プレーヤーズ版」
きちんと知りたいゴルフの基本ルール&マナーまとめ

ゴルフルールの原則はあるがままにプレーすること、つまりティーショットからカップインまではできる限りボールに触れないということです。しかし、どうしてもプレーできない状態になることもあるため、そのときの救済を目的としてルールが存在しています。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、ゴルフ初心者が最低限覚えておけば良い基本的なゴルフマナーをまとめました。これでコースデビューも安心してできます!
2019年ゴルフルール改正のまとめ

2019年1月1日からゴルフルールが大改正されています。今回のルール改正はR&A(ロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフクラブ・オブ・セントアンドリュース)とUSGA(全米ゴルフ協会)が主体となってとりまとめており、ルールを簡素化することで深刻なゴルフ離れを食い止め、ゴルフ人口を増やそうという意図があります。

ゴルフのローカルルールには様々な種類がありますが、それらを適切なタイミングで使うことのできるプレイヤーは意外と少ないように思います。
ローカルルールの適切な使い方を知ると、ラウンドをスムーズに進行することができます。その結果、心にゆとりができ、ゴルフをもっと楽しむことができるようになるでしょう。

ゴルフのペナルティーには多くの種類があり、ややこしいと感じている方も多いのではないでしょうか?ルール違反をした際、救済を受ける際に間違った処置をしてしまうと、悪気は無くとも同伴者からの信頼を失うことになりかねません。人任せにせず、自分でルールを学ぶことも紳士としての役目といえます。

各ホールのスタート地点となるティーイングエリア。出だしからペナルティになるなんてことになると、がっかりですよね。
そのようなことにならないよう、こちらのページではティーイングエリアでのゴルフルールについてまとめています。ぜひお役立てください。

パッティンググリーンは各ホールでパッティングを行うために、芝が短くかられているエリアを指します。「パッティンググリーン」はゴルフ規則上の用語であり、普段のラウンドでは「グリーン」と呼ばれることが一般的です。

誰でもよく入れてしまうバンカーですが、ルールはバッチリですか?
バンカー内では、うっかりやってしまいがちなミスが罰打につながってしまうケースも多いので注意が必要です。

2019年からゴルフ規則が改正され、旧ルールの「スルーザグリーン」は「ジェネラルエリア」に呼称が変わりました。フェアウェイ、ラフなどプレーしているホール内の大部分を占める「ジェネラルエリア」でのルールはとても重要です。
これだけは知っておきたいラウンド時のルールまとめ

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。本記事ではティーグラウンドでのゴルフマナーをまとめています。スタート何分前にティーグラウンドに到着すべきか、同伴者がショット時の立ち位置、前の組への配慮などを解説します。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、フェアウェイでのマナーをご紹介していきます。次のショットへの移動や、同伴者のショット時の立ち振舞いなど、基本的なマナーを確認してラウンドを楽しみましょう!

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、バンカーでのルールやマナーと速やかにプレーするコツをまとめています。意外と知らないレーキの置き方やバンカーの砂の均し方などを解説していきます。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、グリーン上での基本的なゴルフマナーをご紹介します。ピンの抜き差し、ボールマーカーを使ったマークの仕方、ラインを踏んではいけないなど、パッティングの際のマナーを解説!

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回はゴルフ場の乗用カートに関してのマナーやルール、同伴者と楽しくプレーをするためのちょっとした心遣いについてご紹介します。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、ゴルフ初心者が最低限覚えておけば良い基本的なゴルフマナーをまとめました。これでコースデビューも安心してできます!