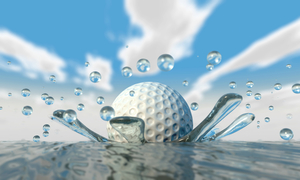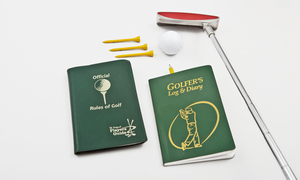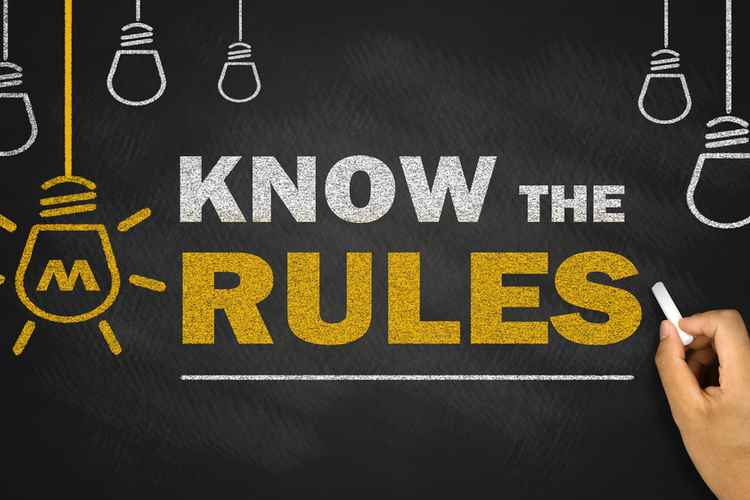
ゴルフルールの原則はあるがままにプレーすること、つまりティーショットからカップインまではできる限りボールに触れないということです。しかし、どうしてもプレーできない状態になることもあるため、そのときの救済を目的としてルールが存在しています。
ゴルフはスポーツには珍しく、審判がいません。ラウンド中の行動については、プレイヤーの誠実さや合理的な判断に委ねられる部分も多く、競技の際は特にプレイヤー自身がしっかりとルールを理解しておく必要があります。
本記事では、ゴルフ初心者にも理解しやすいようにゴルフの基本的なルールをまとめています。ぜひ、お役立てください。
5つのプレーエリアについて

ゴルフコースはルール上、「ティーイングエリア」「ジェネラルエリア」「パッティンググリーン」「バンカー」「ペナルティエリア」の5つに分けられます。
2018年まで適用されていた旧ルールから一部名称や定義が変更になった点もありますので、その点も踏まえながら5つのプレーエリアについてご説明していきます。
ティーイングエリア(旧「ティーインググラウンド」)

ティーイングエリアとは、各ホールでティーショットを打つエリアとなっており、2つのティーマーカーを結んだ線から後方に2クラブレングスがその範囲となっています。
各ゴルフ場は老若男女問わずプレーを楽しめるよう、バックティー、レギュラーティー、フロントティー、レディースティーなど複数のティーイングエリアが整備されていることがほとんどです。
2018年まで適用されていた旧ルールでは、「ティーインググラウンド」という名称で呼ばれていましたが、2019年から施行された新規則で「ティーイングエリア」という名称に変わっています。
ジェネラルエリア(旧「スルー・ザ・グリーン」)

ジェネラルエリアとは、プレーしているホールからその他の4エリアを除いた部分を指します。フェアウェイ、ラフ、修理地やサブグリーンまでがその範囲内となっており、コースの大部分を占めています。
2018年まで適用されていた旧ルールでは「スルー・ザ・グリーン」と呼ばれていましたが、2019年から施行された新規則で「ジェネラルエリア」という呼び方に変わりました。
パッティンググリーン

パッティンググリーンとは、その名の通りパットをするために芝が短く刈り込まれたエリアです。各ホールを締めくくるエリアとなっており、特に繊細なプレーが必要となりますので、パッティンググリーン独自のルールも多く設定されています。
当日のプレーに使用しないサブグリーン は、ルール上は修理地と同じ扱いとなり、ジェネラルエリアに該当します。パッティンググリーンのルールは適用されません。
バンカー

バンカーとはコース内にある砂地を指し、各ホールの戦略性を高めるための障害として配置されています。打つ前にクラブを地面につけることができない上、シチュエーションによっては球と一緒に砂まで打つ「エクスプロージョンショット」という高等技術も必要となります。
バンカー特有のルールを苦手としているプレイヤーも多く、2019年から施行された新規則でも「2打罰でバンカーの外に出せる」など、大きく変更が加えられています。(詳細は後述しています。)
ペナルティエリア(旧「ウォーターハザード」)

ペナルティエリアとは、池やクリーク、崖、林など、球が入ってしまうと打つのが困難な区域を指します。2018年まで適用されていた旧ルールでは、「ウォーターハザード」という名称で池やクリークなどの水域がその範囲として指定されていました。2019年から適用された新規則では、水域以外にもゴルフ場や競技委員会が1打罰での救済を認めたいエリアも指定できるようになり、「ペナルティエリア」という名称に改正されています。
障害物とルースインペディメントについて

ゴルフ規則において、障害物はコース内にあるプレーに影響を与える人工物と定義されており、「動かせない障害物」と「動かせる障害物」に分類されます。プレーに影響がある障害物については基本的に何らかの救済措置が用意されていますが、種類やシチュエーションによってその方法が異なりますので、ルールをよく知っておく必要があります。
動かせない障害物
動かせない障害物が妨げとなり、スイングができない場合は、球が元あった場所から最も近く、ホールに近づかない点(ニヤレストポイント)から1クラブレングス以内の範囲にドロップしてプレーを再開することができます。
【動かせない障害物の例】
・クラブハウスや茶店、お手洗いなどの建造物
・スプリンクラー
・排水溝
・カート道
・ベンチ
・樹木の支柱
動かせる障害物
動かせる障害物が原因で球が打てない、スタンスが取りづらい場合は、不当にプレーを遅れさせないことを条件に、それらを移動させることができます。
【動かせる障害物の例】
・バンカーレーキ
・ペナルティエリアの範囲を示す赤杭・黄杭
・ゴミ箱
・たばこの吸い殻
・ティーマーカー(※ティーショット前に動かすと2打罰)
・カート道の案内看板
障害物に関する注意点①「OB杭は固定物」
ペナルティエリアの範囲を示す赤杭や黄杭は「動かせる障害物」の救済を受けることができます。杭に寄りかかって球が止まっているなど、スイングの邪魔になる場合は杭を一時的に抜くことが許されています。しかし、同じ杭でもジェネラルエリアとOBの境界を示すOB杭(白杭)は「固定物」となっていますので、注意が必要です。スイングの邪魔になったとしても動かすことができず、いかなる理由でも動かした場合には2打の罰が課されます。
障害物に関する注意点②「ペナルティエリア内での救済措置」
ペナルティエリア、バンカー内において「動かせる障害物」は他のエリア同様に無罰で移動させることができますが、「動かせない障害物」に対する救済は適用することができません。
ルースインペディメントについて
ルースインペディメントとはコース内に散在する自然物を指し、プレー中はどのエリアにおいても無罰で取り除くことが認められています。ただし、取り除いたことが原因で球が動いてしまうと1打の罰が課されますのでご注意ください。
2018年まで適用されていた旧ルールでは、ペナルティエリアとバンカーでは取り除くことが認められておらず、違反すると2打のペナルティが課されていました。2019年から施行された新規則ではすべてのエリアで取り除けるようになりました。
【ルースインペディメントの例】
・石
・木の葉や枝
・動物のふん
・虫(ミミズやカナブンなど)
※同じ自然物でも固定されている物、生長物、ボールに付着している物はルースインペディメントではありません。
救済の基点とドロップについて

ルールによる救済を受ける際は、球がある位置から最も近く、ホールに近づかない基点(ニヤレストポイント)を決めて、そこから1クラブレングスまたは2クラブレングスの範囲(ドロップエリア)に球をドロップします。
ニヤレストポイントを決める3つ条件
①球のあった位置から最も近い点であること
②ホールに近づかない点であること
③障害を避けてスタンスが取れること
以上の3つの条件を満たす地点が「ニヤレストポイント」となります。
ドロップの手順
①球のあった位置をマークします。
②救済の基点(ニヤレストポイント)を決めてマークします。
③膝の高さから球をドロップします。
ドロップエリアの範囲内に球が止まれば、そこからプレーを再開し、ドロップエリアから出てしまった場合は再ドロップが必要になります。再ドロップしても範囲内に球が止まらない場合は、2度目のドロップが最初に接地した点にプレースしてからプレーを再開します。
ゴルフ用具について

携帯するクラブの本数
ゴルフのラウンド中に使用できるクラブの本数は14本までと決まっています。15本以上のクラブを携帯していた場合は罰則規定の対象となり、1ホールあたり2打のペナルティ、1ラウンドで最大4打のペナルティが課されます。15本のクラブを使用した場合は競技失格となります。
ラウンド中にクラブの本数が多いことに気づいた際は、まず不使用宣言をします。1ホール目に気づいた場合はそのホールのスコアに2打を加算し、2ホール目以降に気づいた場合は、最初の2ホールにそれぞれ2打ずつペナルティを加算します。
不適合クラブの携帯
ラウンドで使用するクラブは、長さや重量、ヘッドの形状、性能などに規定があり、それに反するクラブの携帯、使用は禁止されています。不適合クラブをストロークに使用した場合は競技失格、携帯していた場合は15本目のクラブと同様に1ホールにつき2打罰、1ラウンドで最大4打の罰を加算しなくてはなりません。
公認球と非公認球
ラウンド中に使用するボールは、ルールに適合す公認球でなければなりません。大きさや重量、飛距離性能など細かい基準が定められています。プライベートなラウンドでは非公認の高反発球を使われる方もいらっしゃいますが、公式競技では使用できませんので注意が必要です。
ボールの装飾
ボールに矢印やラインを書き込んだり、識別用のシールを貼ったりすることはルールで認められています。同伴競技者と同じボールを使う際は、自分の球を識別できるよう目印をつけておくようにしましょう。
ティーイングエリア外からのショット(通称:でべそ)

通称でべそと呼ばれるティーイングエリア外からのショット
ティーイングエリアの範囲は2つのティーマーカーを結ぶ直線から後方に2クラブレングス以内と定められています。その範囲外にティーアップしてストロークすると2打のペナルティが課され、3打目として正しい位置から打ち直すことになります。エリア外からのストロークは通称「でべそ」と言われており、うっかりやってしまうルール違反の代表格となっています。
※罰打の対象となるのは、ティーアップした球がティーイングエリア外に出ていた場合のみで、スタンスがエリア外に出ても問題はありません。
OB、ロストボール、暫定球

OB、ロストボールの処置
打った球がOBまたはロストボールとなった際は、1打のペナルティを加算して元の位置から打ち直さなければなりません。ティーショットがOBまたはロストボールの場合は3打目としてティーショットを打ち直し、2打目がOBまたはらロストボールの場合は4打目として2打目地点から打ち直すことになります。
暫定球
OBやロストボールのたびに打ち直すとプレーの効率が下がってしまいますので、OBやロストボールの可能性がある場合は暫定球を打つことになります。ティーショットにOBまたはロストボールの可能性がある場合は、3打目として暫定球を打ちます。次打地点に到着して、初球が見つかった場合は2打目としてプレーし、見つからなかった場合は暫定球を4打目としてプレーします。
※ボールの捜索時間は3分と定められており、3分経過後に初球が見つかったとしてもロストボール扱いとなります。2018年まで適用されていた旧ルールでは球の捜索時間は5分でしたが、2019年から施行された新規則で3分に短縮されています。
前進2打罰について
2019年から施行された新規則で「前進2打罰」というローカルルールが追加されました。これはOBやロストボールの際に打ち直しをせず、球を紛失した地点付近から2打罰でプレーを再開できるというものです。ただし、このルールはプライベートなラウンドの効率化を目的としており、公式競技では適用できません。競技に出場される方はお間違いのないよう、ご注意ください。
空振りについて
ゴルフルールの中ではよく「ストローク」という単語が使われます。初心者の方は馴染みのない単語かもしれませんが、ストロークとは「打つ意思を持ってクラブをスイングすること」を指します。打つ意思を持て振り、クラブが球を通過した時点でストロークは成立し、1打とされます。プライベートなラウンドでは空振りを大目に見ることも多々ありますが、ルール上はスコアに1打としてカウントしなければなりません。
球の確認について
深いラフに埋もれている、バンカーで目玉になっているなど、プレーしようとしている球が自分のものであるか、わからなくなることがあります。ゴルフ規則では球の確認が目的であれば、プレー中の球を拾い上げることができます。(2018年まで施行されていた旧ルールでは球を拾い上げる際は同伴競技者への告知が必要とされていましたが、2019年から施行された新規則ではそれが不要となりました。)
ピックアップした球に汚れが付着していて確認が難しい場合は、必要最小限の汚れを取り除くことができますが、必要以上の汚れを取ると、1打のペナルティが課されます。球の確認が済んだ後は、元通りのライに戻してプレーを再開します。
球を動かした(動いた)際の対処について
プレー中に球が動いてしまうことはよくあり、故意でない場合は無罰となることが多いのですが、そうでないケースも存在します。プレーしているエリアや動いた原因によって罰打が加算されるかが異なります。ティーイングエリアやパッティンググリーンでは、打つ意思がない場合は基本的に無罰、その他のエリアでは打つ意思がなくとも、球が動いた原因がプレイヤーにあることが明確な場合は1打のペナルティが課されます。以下に無罰のケース、1打罰となるケースをまとめていますので、ご確認ください。
【無罰で元の位置に戻してプレーを再開】
・風で球が動いた
・ティーイングエリアでアドレスを取っているときにクラブが当たって球がティーから落ちた
・ボールの捜索中に蹴ってしまった
・グリーン上でマークする動作の前後に球を動かしてしまった
【1打罰で元の位置に戻してプレーを再開】
・アドレス時にクラブが当たったことにより球が動いた(※ティーイングエリア、パッティングエリアでは無罰)
・ラフでクラブをソールしたことが原因で球が動いた
・素振りによって球が動いた(※ティーイングエリア、パッティングエリアでは無罰)
ライ、スイング区域の改善について

ライの改善
ゴルフでは、プレー中の球の状態(芝の状態や傾斜など)を「ライ」といいます。前述したように、ゴルフルールの原則には「あるがまま」にプレーするという項目が含まれています。ライを不当に改善し、「あるがまま」の状態を崩すことはルールで禁止されており、違反した場合は2打の罰が課されます。
【ライの改善の例】
・打つ前にボールの後ろの芝を踏んで固める(※ティーイングエリアでは無罰)
・足場の悪い傾斜地でスタンスを取りやすくするために地面を踏んで窪ませる
スイング区域の改善
スイングの区域を改善することも禁止されており、ライの改善と同様に違反した場合は2打の罰が課されます。素振りの際などは、意図的でなくともスイング区域を改善してしまうこともあります。不注意でペナルティを受けてしまうことにならないよう、お気をつけください。
【スイング区域の改善の例】
・スイングの邪魔になる位置になる木の枝を折った、枝同士を絡ませてスペースを確保する
・素振りが当たって木の葉を落とす
※上記のような項目は打つ前であれば、罰打の対象となりますが、ストローク中に偶然、枝が折れてしまった、木の葉を落としてしまったという場合は無罰です。
アンプレヤブルについて

アンプレイヤブルとは?
アンプレヤブルとはストロークが困難な位置に球がある際に、1打罰を受けて球を移動させる、もしくは打ち直すことができる救済措置です。1打罰を受けてアンプレヤブルの救済を受ける際には以下の3つの選択肢があります。
①球があった位置から2クラブレングスかつホールに近づかない範囲にドロップ
②ホールと球の後方線上にドロップ
➂元の場所に戻って打ち直し
※バンカー内でアンプレヤブルを適用し、①または②の救済を受ける場合、ドロップするエリアはバンカー内に限られます。
バンカー内でのアンプレヤブルに関するルール追加
2019年から施行された新規則では、バンカー内でアンプレヤブルを適用する際、上記の3つの選択肢に、「④2打罰で球とバンカーを結ぶ後方線上(バンカー外)にドロップ」が追加されています。
グリーン周辺でのルール改正について

グリーン上でのマークについて
グリーン上では、球の後ろをマークしてピックアップすることができます。マークせずに球を拾い上げた場合には1打のペナルティが課されます。同伴競技者のライン上に自分の球がある場合には、目印を決めてマークの位置をずらすのがマナーとされています。
グリーン上の修復について
2018年まで適用されていた旧ルールでは、グリーン上で修復が認められているのはボールマークとホールの埋跡に限られていました。2019年から施行された新規則ではスパイクマークや動物の足跡など、他の損傷個所の修復も認められています。
ピン(旗竿)の取り扱いについて
2018年まで適用されていた旧ルールでは、ピン(旗竿)を指したままパッティングを行い、カップインすると2打の罰を加算しなくてはなりませんでした。2019年から施行された新規則では、それが無罰となり、パッティングの際にピンを抜くかどうか選択できるようになりました。
OKパットについて
OKパットとは、パッティングした球がほぼ間違いなく入る距離まで寄ったときに、同伴競技者の許可があれば最後の1打を省略できるというルールです。公式競技においては、マッチプレーでは適用できますが、ストロークプレーでの適用は認められていません。
※プライベートなラウンドであれば、プレー効率を高めるために、ストロークプレーでも「OKパット」が頻繁に使われます。OKとする基準は1グリップ(約25cm)が一般的です。
ペナルティエリアでの救済措置について

ペナルティエリアには、水域や崖などゴルフ場や競技委員会が1打罰での救済を認めたいエリアが指定されています。その範囲を指定する杭の色によって、救済方法が異なり、黄杭に囲まれている「イエローペナルティエリア(旧:ウォーターハザード)、赤杭に囲まれている「レッドペナルティエリア(旧:ラテラルウォーターハザード)の2種類があります。
イエローペナルティエリアからの救済
イエローペナルティエリアから救済には以下の3つの選択肢があり、いずれも罰打は1打となっています。
①球が最後にエリアの境界線を横切った点から1クラブレングス以内かつホールに近づかないエリアにドロップ
②球が最後にエリアの境界線を横切った点とホールの後方線上にドロップ
➂元の位置に戻って打ち直し
レッドペナルティエリアからの救済
レッドペナルティエリアはホールのサイド一面に池が伸びている場合など、主に後方線上の救済が困難な区域が指定されています。救済を受ける際は上記の①~➂に加えて、「④球が最後にエリアの境界線を横切った点から2クラブレングスかつホールに近づかない範囲内にドロップする」も選択できます。
バンカーでは打つ前のソールはNG

バンカー内では、ショットの前にソールする(クラブを地面につける)ことが認められておらず、違反すると2打のペナルティが課されます。バックスイングや素振りが砂に触れてしまった場合も罰打の対象となりますのでお気を付けください。
ペナルティエリア内でのソール
2018年まで適用されていた旧ルールでは、ペナルティエリア内でもショット前のソールは認められておらず、バンカーと同様に違反した場合は2打の罰を加算しなければなりませんでした。2019年から施行された新規則では、それが無罰となり、ペナルティエリア内からもジェネラルエリアと同じようにプレーできるようになりました。
その他のルール改正

2度打ちと自打球
自打球とはストロークした球がプレイヤー自身やそのキャディーさん、携帯品(キャディーバッグやカートなど)に当たること、2度打ちとは1回のストロークで2回以上クラブに当たることを指します。
2018年まで適用されていた旧規則では、どちらも1打のペナルティが課されていましたが、2019年から施行された新ルールでは無罰に変わっています。(ただし、故意に行った場合は従来通り1打罰となります。)
自打球、2度打ちがあった後の球はあるがままの位置からプレーを続行します。
誤球と誤所からのプレーについて
誤球とは自分以外のプレイヤーの球を打つこと、誤所からのプレーとは本来プレーすべき位置ではないところからストロークすることです。どちらも2打のペナルティを受け、正しい位置から打ち直すこととなります。
【誤球が起こりやすいケース】
誤球が起こりやすいのは、芝や砂に埋もれて自分の球であるかの確認がとりづらい状況や、同伴者とボールのブランドや番号がかぶった時などです。球の確認を怠らないこと、自分の球に識別マークを付けておくことを意識しておくと、誤球を未然に防ぐことができます。
【誤所からのプレーが起こりやすいケース】
誤所からのプレーにはティーイングエリアを間違える、救済を受ける際の基点やドロップエリアの設定が間違えるといった例が該当します。救済の基点やドロップエリアの範囲は状況によって異なりますので、お間違いのないようご注意ください。
プレーに係わるアドバイスについて
ゴルフ規則では、自分の関係者(キャディーさんなど)以外の人からアドバイスを受けることが禁止されています。逆に、同伴競技者へ助言をすることも禁止されており、どちらも違反した場合は2打のペナルティを受けなければなりません。
プライベートなラウンドでは、プレイヤー同士でアドバイスを送り合っている方も多いかと思います。同伴者と一緒に戦略を練るのもひとつの楽しみですが、公式競技となると、それが反則となってしまいますのでご注意ください。
※ティーイングエリアからバンカーまでの距離など、コース図から誰もが把握できるような情報は「公知の事実」とされており、教えたとしてもドバイスには該当せず、罰打の対象にもなりません。
まとめ
ゴルフの基本ルールは確認できましたでしょうか?
ラウンドのスコア以前に、ルールやマナーを守るというのは、紳士・淑女として大切なことです。ゴルフは審判のいないスポーツですから、プレイヤー自身の知識やモラルがより一層重要となります。
ルールを知ることで戦略の組み立てにも幅が出てくるかもしれません。本記事が皆様のゴルフライフをさらに充実させるきっかけとなれば幸いです。
ラウンド時に持ち歩ける「JGA 2019年ゴルフ規則プレーヤーズ版」
2019年ゴルフルール改正のまとめ

2019年1月1日からゴルフルールが大改正されています。今回のルール改正はR&A(ロイヤル・アンド・エンシェント・ゴルフクラブ・オブ・セントアンドリュース)とUSGA(全米ゴルフ協会)が主体となってとりまとめており、ルールを簡素化することで深刻なゴルフ離れを食い止め、ゴルフ人口を増やそうという意図があります。

ゴルフのローカルルールには様々な種類がありますが、それらを適切なタイミングで使うことのできるプレイヤーは意外と少ないように思います。
ローカルルールの適切な使い方を知ると、ラウンドをスムーズに進行することができます。その結果、心にゆとりができ、ゴルフをもっと楽しむことができるようになるでしょう。

ゴルフのペナルティーには多くの種類があり、ややこしいと感じている方も多いのではないでしょうか?ルール違反をした際、救済を受ける際に間違った処置をしてしまうと、悪気は無くとも同伴者からの信頼を失うことになりかねません。人任せにせず、自分でルールを学ぶことも紳士としての役目といえます。

各ホールのスタート地点となるティーイングエリア。出だしからペナルティになるなんてことになると、がっかりですよね。
そのようなことにならないよう、こちらのページではティーイングエリアでのゴルフルールについてまとめています。ぜひお役立てください。

パッティンググリーンは各ホールでパッティングを行うために、芝が短くかられているエリアを指します。「パッティンググリーン」はゴルフ規則上の用語であり、普段のラウンドでは「グリーン」と呼ばれることが一般的です。

誰でもよく入れてしまうバンカーですが、ルールはバッチリですか?
バンカー内では、うっかりやってしまいがちなミスが罰打につながってしまうケースも多いので注意が必要です。

2019年からゴルフ規則が改正され、旧ルールの「スルーザグリーン」は「ジェネラルエリア」に呼称が変わりました。フェアウェイ、ラフなどプレーしているホール内の大部分を占める「ジェネラルエリア」でのルールはとても重要です。
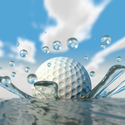
ゴルフルールのややこしい点の代表例が池などの「ペナルティエリア」に関する項目です。赤杭と黄杭で救済の方法が違ったり、救済の基点の決め方が難しかったりで、救済措置を間違えやすいエリアとなっています。
これだけは知っておきたいラウンド時のマナーまとめ

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。本記事ではティーグラウンドでのゴルフマナーをまとめています。スタート何分前にティーグラウンドに到着すべきか、同伴者がショット時の立ち位置、前の組への配慮などを解説します。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、フェアウェイでのマナーをご紹介していきます。次のショットへの移動や、同伴者のショット時の立ち振舞いなど、基本的なマナーを確認してラウンドを楽しみましょう!

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、バンカーでのルールやマナーと速やかにプレーするコツをまとめています。意外と知らないレーキの置き方やバンカーの砂の均し方などを解説していきます。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、グリーン上での基本的なゴルフマナーをご紹介します。ピンの抜き差し、ボールマーカーを使ったマークの仕方、ラインを踏んではいけないなど、パッティングの際のマナーを解説!

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回はゴルフ場の乗用カートに関してのマナーやルール、同伴者と楽しくプレーをするためのちょっとした心遣いについてご紹介します。

ゴルフには沢山のルールやマナーが存在しており、初心者ゴルファーやこれからゴルフを始めようとする方にとって大きなハードルになるのではないでしょうか。今回は、ゴルフ初心者が最低限覚えておけば良い基本的なゴルフマナーをまとめました。これでコースデビューも安心してできます!